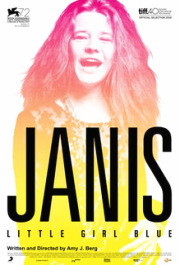
とても面白かった。私にはこの映画のジャニスは、「普通」の苦悩を数多く背負った者に見えた。
薬物についても、彼女が特別なんじゃなく、誰にでも起こりうることとして描かれていた。彼女が薬物を使っていたのは、たまたまあったから、変な言い方だけども「あってしまった」から、という感じを受けた。だから映画が、ジャニスの死後に番組に出演したジョン・レノンの「薬物を撲滅するにはどうしたらよいか」への答えで終わるのもさもありなんと思った。
映画は、「なぜ歌うのか」と問われたジャニスの答えに始まる。いわく「歌うことで色々な感情を体験できるから」。続けて「歌は感情から生まれて感情を生む」「お客にはリズムを感じて踊って欲しい」。次いでの「Tell Mama」のステージに圧倒される。
オースティン時代の友人(ジャニスが紛れ込んだ「boys」の一人)は「あのトラブルメイカーにあんな『特技』があったなんてと驚いた」と語るが、先の言葉からも分かるように、彼女にとって歌とはまず手段である。「Amy」(感想)が、歌わずにいられないがスターにはなりたくなかったエイミーの「普通の女の子」願望を描いていたのと異なり、本作は、「可愛い少女」になれなかったジャニスが「特技」でもってスターになり色んな男といちゃこらする様を描く。ぱっとしない男がスターになっていい目を見る(でもって悩みもする)のとそう変わらないから、見ていて気が楽だ。だから、私が最も「適切」に思われた彼女についての言葉は、メリッサ・エスリッジの「女で初めてロックスターになって、脚光を浴びた」というシンプルな言い方である。
ポートアーサーでの少女時代を表すのに、妹のローラの「姉は成長する毎にグラビアの美少女とかけ離れていった」との言葉と共に、ジャニスの描いた「this is pretty girl」の絵と年代順に並べられた彼女自身の写真、差別に反対して虐められていたという高校生当時の、彼女はしゃんと立っているが背後の影は老いた岩のように見える写真などが使われており、この辺りで、「真実」はどうあれ、私の好きな「的確にピンをうってくる」タイプの映画だと分かって惹き込まれる。
「はみ出し者」だったジャニスが、サンフランシスコに舞い戻って音楽仲間と撮った写真を「私の格好が普通に見えるでしょ?」と両親に送るのには、一人暮らしを始めたころ、訪ねて来た両親に本とCDで溢れかえった部屋に溜息をつかれたので、「TOKYO STYLE」に「これが普通です」と添えて送ったのを思い出した(あんなことをするなんて、私も若かった!笑)妹が語る両親にとってのジャニスや、死後にファンレターを公の場で読む母親の姿などからは、色々なことがあったのだろうとしか言えないが、ジャニスが両親に宛てた手紙の内容からは、彼女の頭の中に常に家族があったことが分かる。
「フェスティバル・エクスプレス」の頃のインタビューで「ウーマンリブの運動家には、あなたは女を武器にしていると言う人もいます」「メンバーに女がいないのをいぶかる声も」と言われたジャニスは、「初耳よ」「男を独占したいから」と笑い飛ばす。「女で初めてのロックスター」だったということは、そもそもミュージシャンとは男ばかりだったのだろうから、そうなるのも致し方ないとまず考えた。それから、私も20代の頃は色々な男性と過ごすのに忙しくて同性との時間が無く、当時から「フェミニスト」の自覚はあったけど一抹の疑問を感じてもいたのを思い出した。そうなってしまう何かがあるのではないか?
ともあれ、作中ジャニスについて語る数多の関係者のうち、女性は幼馴染、妹、恋人のみで、後は全て男性である。男達は彼女の魅力を様々に語る、陽気だった、物静かだった、自然体だった、頭がよかった、カリスマ性があった…このてんでなところがいい。「サマータイム」のレコーディング中、「これで決まり」と言い放ち出て行こうとするジャニスをメンバーが呼び止めるとおどけて振り返る姿のチャーミングなこと。「フォトジェニック」さを感じる写真も多々あり、彼女の魅力を改めて知った。「Pearl」のジャケ写を撮った時、少なくとも一つの要素についてはジャニスが希望に満ちていたことを知ることが出来たのは嬉しかった。