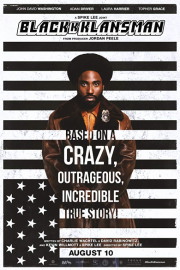
この映画は「映画が影響を与えない、などということはあり得ない」と訴えているのだから、見ている間は幾らか笑ったり快哉を叫んだりすることが出来ようとも家に持って帰るのはこれだ、と最後に喉に岩を突っ込まれるのが当然なのだ。クライマックスでは作中のハリー・ベラフォンテが覗き見たのと同じものを何十年も後に主人公ロン(ジョン・デヴィッド・ワシントン)が窓から覗き見、更に何十年後かの私達がそれをスクリーンの中に見ているという構造が明かされる。映画の中では登場人物が起きられなかった、起きろ、起きた、とやっていたが最終的には私達が起きなきゃ意味がないのだ。
心に残るのはロンとパトリス(ローラ・ハリアー)の会話で露わになる二人の間のずれ。「今の黒人映画はファンタジー」「パム・グリアは嫌い?」「『コフィー』はうそ、現実は警察が黒人を殺してる」「タマラ・ドブソンは?」「黒人のイメージを悪くしてる」「たかが映画じゃないか」。「活動なんかして何か変わるのか」「あなたはなぜ警官なんかやってるの」「警察を中から変えるんだ」。特に後者のずれは最後まで解消されないが、それでも彼らが揃って銃を構えるのに映画は終わる。抑圧されている者達の中で更なる属性の違いによって亀裂ができそうになるという問題は「ビール・ストリートの恋人たち」にも描かれていたが、あちらは愛で、スパイク・リーは力づくでその亀裂を埋める。埋めなきゃならないから。
パトリスが警官に暴力を振るわれたことを語る背景に「Too Late to Turn Back Now」が流れているの(からのあのダンスシーン)に、このセンスは当事者にしかない、いや使えないものだと思った。ああいう目に遭っている彼女が「コフィー」は好きじゃないと言う、「警官が皆ああじゃない」と言われても「一人いれば嫌いになるには十分」と返す、その気持ちはよく分かる。でもロンのように自身が警察になる者も必要なのだ。見ながらずっと昔に「キャノンボール2」を見た時ふと疑問が生じてフェミニズム(なんて言葉は知らなかったけれども)の種が心に撒かれたことを思い出した。警察がどんな組織であろうと、自分が警察になる、あるいは女の警官が増えることには意味があるんじゃないかと(ここでの「警察」とはどんな形であれ何らかの力を持つ存在ということ)。
フリップ(アダム・ドライバー)は潜入捜査も佳境に入ってから「これまで自分をユダヤ人と意識したことはなかったが今は毎日意識している」と口にする。捜査開始時に同僚ジミー(マイケル・ブシェミ)の「ネックレスは外したらどうだ」に「これはダビデの星だ」と返してそのまま出ていくのは、こだわりが強かったのではなく自分を差別する者がいると実感していなかったのだと推測される。フェリックスの「ユダ公か?」に「侮辱するな」と返す場面でその顔が初めて大写しになるのは、あの時に彼が目覚めたからである。同様に「ホロコーストはなかった」に「あれは素晴らしい」といわば逃げるのには、抑圧を受ける者こそ抑圧する者のやりそうなこと、更にそれを上回ることを知っている、装えるのだと思った。私達はそれをうまく使わなきゃ、あるいは使われた時には気付かなきゃならない。